エニアグラムには、「囚われ」という強く意識してしまう、あるいは絶対に認めたくない感情が存在します。
例えば「自分は絶対に怒らない!怒るのはよくないからだ!」とか、あるいは「いろんな不安要素が気になって夜も眠れない」とか、9つのタイプにそれぞれ強く意識してしまう感情や気持ちがあります。
で、今回はその感情……ではなく、強く囚われてしまう気持ちや感情の出所について見ていきましょう。
子供時代の経験が性格を形成する

各タイプの囚われや歪みを構築してしまう元となったものが、幼少期に親から受け取った何かしらのメッセージ、そして主に親子関係の問題をもとに性格が形成された「こうすれば問題解決できるんだ!」という自分なりの攻略法です。
例えば夜泣きする子供に毎回「うるさい!」「静かにしろ!」と怒鳴り散らして黙らせていれば、「どれだけつらくても、ずっと我慢しないといけないんだ」と子供は学びます。
あるいは親が「これをしなさい」「これが正しいんだ!」と子供の行動を代わりに選択すれば、「自分は何も決めなくていいし、決める権利もない」と学び、決断力がなくなってしまいます。
当然、これらの特徴は大人になっても繰り越されます。「迷惑をかけるくらいなら死んだ方がいい」と考える人や、いつまでも親離れできない優柔不断な人が今回例に挙げた子供たちの将来。
幼少期から受けてきた親からのメッセージは、それだけ大きいのです。
私たちの性格は、もって生まれた気質の力を借りて、子ども時代の傷を防衛し、埋め合わせます。子ども時代に遭遇した難事を切り抜けていくために、私たちは限定された対応方法や自己イメージ、行動などを無意識に学びました。それによって、子ども時代になんとか対処し、生存することが可能だったのです。
したがって、誰もが特定の対応方法の「専門家」となる一方で、それが過剰に使われると、性格の中でうまく機能しない中心部分にもなってしまうのです。
ー中略ー
このように本質とのつながり失うことが深い不安を引き起こし、九つの「とらわれ」のどれかとなって現れます。
新版エニアグラム 自分を知る9つのタイプ P54,55より引用
要するに、
- 我々は小さい時に何かしら起きた問題に対して、自分なりの対処法を身につけた
- 自分なりの対処法について精通した一方で、特定の方法に頼ったせいで偏りが生まれた
- 自分の中で性格となって歪みが生まれて本質のどこかが欠落した結果、その欠落部分が囚われになっている
と、端的にまとめるとこういうことですね。
純粋無垢な赤ちゃんも、いろんな経験をすることで良くも悪くも性格が形成されます。それらは赤ちゃん自身が感じた物足りなさや不安かもしれませんし、命の危険かもしれません。
当然赤ちゃん側も座して死を待つなんてことはせずに、精一杯足掻きます。
- どんな問題が発生して
- その問題にどういう方法で足掻いたのか
これが性格、ひいてはエニアグラムにおける根源的恐れや欲求、そして囚われに結びついていくわけですね。
親から受けたメッセージと根源的恐れ
当然、問題の大小は家庭によりますし、それこそ具体的な事例や子供本人の捉え方などは「人それぞれ」としか言いようがありません。
ですが、大きな分類を決めてそこに振り分けることならばできなくはありません。
エニアグラムでも、「幼少期の自分が親からどのようなメッセージを受けのか」をそれぞれのタイプに分けて考えられています。
そして「どういうメッセージを受けたのか」を元に「根源的恐れ」「根源的欲求」と続いていき、囚われへと向かっていくのです。
幼少期に受けた親からのメッセージ
親も万能ではありません。時には間違えますし、子供に意見を押し付ける事も世話しきれずに「それくらいどうにかしてよ!」と世話を放棄してしまう事もあるでしょう。
これらは全部仕方ない事ではあるのですが、やはり子供にはそんな事わかりません。
自分が生きるため、満足するために欲しいものは、親の状態を気にせず何でも要求してきます。興味を持った事は何でもしますし、自分の気持ちを正直に表現します。
ですが、その全部が許されるわけではありません。当然ダメなものはダメと叱られますし、親の価値観や余裕によって許されるものとそうでないものもあるでしょう。
そんな親からの「No」の中で特に強烈に影響されたものが、タイプの形成に大きく関わっているわけです。
というわけで、以下がエニアグラムにおける「親から受けたメッセージ」の一覧です。「新版エニアグラム 」から直接引用してみましょう。
| 1 | 間違えるのは、よくない |
| 2 | 自分のニーズがあっては、よくない |
| 3 | 自分なりの気持ちや自分らしさがあっては、よくない |
| 4 | うまく生きられたり、幸せすぎるのは、よくない |
| 5 | 世界の中で心地よくいるのは、よくない |
| 6 | 自分自身を信頼するのは、よくない |
| 7 | いかなることでも人を頼るのは、よくない |
| 8 | 弱みがあったり、人を信頼するのは、よくない |
| 9 | 自己主張するのは、よくない |

まあ、ここまで露骨でハッキリした言葉をぶつけられるのも稀でしょうがね。
例えば親が忙しくて「少しは自分でやって!」とつい怒ってしまうと「頼るのはよくないのか」と学んだり(タイプ7)、悩んでる子供に見かねて親が何でも決めてしまうと「自分で最終決定するのはダメなのか(タイプ6)」「自分の意見は言っちゃダメなのか(タイプ9)」となったり……
些細なことでも、性格形成のきっかけになります
根源的恐れ
唯一自分を守ってくれる親から強烈なメッセージや怒り、嫉妬などを受けた子供は、当然「親から見捨てられるかも」と強い不安を覚えます。
そのため可能な限り親の都合がいいように育とうとしますが、ある時(割と早い段階から)「親も全部わかるわけじゃないし、全部できるわけじゃないな」と思い至り、「親からはどうやっても貰えないものもある」と悟るようになります。
「自分にも親の育て方にも、何か大事なものが決定的に足りていない」と、そんなことを思い至った子供は、無意識に漠然と不安や欠落感を覚えます。
この無意識の不安や欠落感が、根源的恐れと言われていますね。
| 1 | 自分が悪く、堕落し、よこしまで、欠陥があることを恐れる |
| 2 | 自分が愛されるにふさわしくないことを恐れる |
| 3 | 自分に価値がないこと、本来価値をもっていないことを恐れる |
| 4 | アイデンティティや個人としての存在意義をもっていないことを恐れる |
| 5 | 役に立たず、無力で、無能であることを恐れる |
| 6 | 支えや導きを持たないことを恐れる |
| 7 | 必要なものを奪われ、痛みから逃げられないことを恐れる |
| 8 | 他者に傷つけられ、コントロールされることを恐れる |
| 9 | つながりの喪失、分裂を恐れる |

だいぶ各タイプの輪郭が見えてきましたね。
ところで「親が万能じゃない」と思い至る「ある時」っていつなんでしょうか?
第一時反抗期?
根源的欲求
さて、親の無力を悟った子供は、漠然としながらも強烈な恐れを覚えるようになりました。
あとは、この恐れや不安、欠落感を自分でどうにかしていくしかありません。
強烈な根源的恐れに対処するために、子供たちは「こうなりたい!」という理想と、理想に執着するあまり屈折した欲望に陥ることがあります。
最後に根源的欲求(左)と、その強さによる屈折(真ん中)を、囚われ(右)と一緒に見てみましょう。
| 1 | 高潔でありたい | 批判的完璧主義に陥る | 囚われ:怒り |
| 2 | 愛されたい | 必要とされたいというニーズに陥る | 囚われ:プライド |
| 3 | 価値ある存在でいたい | 成功の追求に陥る | 囚われ:欺き |
| 4 | 自分自身でありたい | 自己放縦(無軌道で身勝手)に陥る | 囚われ:嫉妬 |
| 5 | 有能でありたい | 無用な専門家に陥る | 囚われ:ためこみ |
| 6 | 安全でありたい | 信じている考えに対する執着に陥る | 囚われ:恐怖 |
| 7 | 幸福でありたい | 必死の現実逃避に陥る | 囚われ:貪欲 |
| 8 | 自分自身を守りたい | たえざる闘いに陥る | 囚われ:欲望 |
| 9 | 平和でありたい | 頑固な怠惰に陥る | 囚われ:怠惰 |
詳しくは以下にも記載しております。そちらも併せてご覧くださいませ。
性格とは「心の傷を癒すためのもの」
エニアグラムの巨匠とされるドン・リチャード・リソは、人の性格を以下のように表現しています。
性格はギプスのようなもの、骨折した腕や脚を守ります。もとの傷がひどければひどいほど、ギプスは大きなものでなければなりません。
もちろんギプスは、手脚が癒え、その完全な機能を回復するために必要です。けれどもそれを外さないと、手脚を使うことが非常に制限され、それ以上成長することができなくなってしまいます。
新版エニアグラム 自分を知る9つのタイプ P 65より引用
要するに、「性格は自分の本質を守るためにできた防護機能で、本質ではない」ということですね。
個人的には全面的に正しい言葉とは思いませんが……それでも、過去のつらい経験や大きな失敗などで歪められた部分がないとは言えません。
自分の歪みを知るために、幼少期のメッセージを知り、根源的恐れを知り、囚われを知る。
このプロセスも、自分がより気を楽に生きていくには必要な要素なのではないでしょうか?
筆者:春眠ねむむ
X :@nemukedesiniso
threads:@shunmin.nemui
参考書籍
タイプ一覧
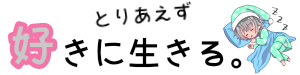



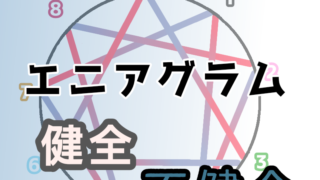





コメント
突然失礼します。
この記事に関して疑問があるのですが、よろしいでしょうか。
囚われや根源的な恐れというのは幼少期に親から受け取った(マイナス面の?)メッセージにより作られる
と受け取ったのですが、それならば、もし親から負のメッセージを与えられずに、本当に幸せな環境で育った子がいれば
その子は囚われや根源的な恐れを持たない人に成長し、どのタイプにも分類されない子というのがいるのでは無いでしょうか。その辺はどういう考察をしますでしょうか
実際、私はこの記事を見て、囚われや根源的な恐れを作ってしまわないような子育てを行って成功しているんではないかという例を
創作物の中の登場人物の話で実在しませんが一例だけ思いつきました。
高木さん大好き様
コメントありがとうございます!
非常に興味深い内容ですね。実は大変わくわくしながら返答を悩んでいました。
さて、以下がご質問に対する私の返答になります。
まず、現実的に完璧に根源的恐れを抱かないような育て方は不可能です。どれだけお世話をしても、人間必ずこじつけでも悪い面を見つけてしまうもので、どのように育てても神様でもない限り負のメッセージを感じ取ってしまうのではないかなと。
それでも完璧に神様に育てられた場合どうなるのか。これに関しては、やはり周囲の風土、環境に左右されてタイプが出来上がるのではないかなと思われます。例えば近所のおじさんだったり、幼稚園や小学校の先生や周囲の同級生だったり、影響を受けるものは必ずしもひとつとは限りません。
先述のとおりどれだけ完璧な環境を用意されても、赤ちゃんも人間ですので、こじつけ的に悪いところを探し出すと思います。この場合、それが性格の形成へとつながるのではないでしょうか?
ただ、普通の人になるとは考えづらいですね。きっと「究極何かしらのタイプには当てはまるものの、そのタイプの判別がよくわからないほどに健全な状態」に育つことでしょう。
エニアグラム書籍の中にも「性格は心のギプス」という言葉がありまして、健全になればなるほど囚われや根源的恐怖を物ともせず、性格という心の壁を必要としなくなるといった記述があります。
つまり健全度1、最高の状態であれば、性格の癖らしい癖がほぼ完全に無くなった状態と言われているわけですね。
よって、完璧に育てられた子供はどうなるかというご質問に対しては、「風土環境に左右されて何かしらのタイプには当てはまるが、性格と言える癖をほとんど必要としない健全度最高の状態となる」というのが私の回答になります。
こんなところでいかがでしょうか?疑問点等ありましたらいつでもご指摘ください。