今回はちょっとした考察回です。
サイコパスだの何だのと言われるような結構エグい性格をしたタイプ8ですが、その子供時代、特に性格が形成されて間もない時や幼年期にどういう感じの過ごし方をしているのかを考えてみたいと思います。
いつものことではありますが、今回も書籍にあることないこと書いていくので、情報収集目的の方は要注意です。
一般的なタイプ8の子供時代
何を知るにも、まずは一般的なタイプ8を知らないことには意味がありません。まずはタイプ8の一般的な子供時代……もとい、親への定位を見ていきましょう。
幼い子供の時、タイプ8は養育者像に愛憎半ばする感情を持った。養育者像とは発達の初期段階で子供の鏡となり、子供の世話をし、愛情と人としての価値観を与えた人物のことである。
―中略―
タイプ8はこの養育者像と強く結びついたり一体化したことがなく、心理的に全く切り離されていたのでもなかった。その結果、養育者像とある種の結びつきを保ち、また、養育者像を補う役割を自分が果たすことで家庭の仕組みに適応することを学んだ。
性格のタイプ P392
養育者像は母性と関連した多くの性質を表して見せてくれた。それは温かさであり、親身の世話であり、教育、承認、優しさ、感受性であった。こういったことで、タイプ8は家長を補完する役割と一体化し、さらには、価値観、愛情、養育などを得るための最善の方法は「強い人間になること」であると学んだ。
タイプ8の子どもは、自分を鍛え上げようと、果敢に挑戦できる行動的なところがあります。また、自分の力だけを頼りに一直線につき進もうとするので、過激になることがあり、それを阻止したり過干渉してくる親を嫌い避けます。従って、自分をどこまでも信じて静観して見守ってくれる親を心の奥深くで求めています。
―中略―
タイプ8の子どもは我が強く、自分の意思を必ず通そうとするため、やさしくて甘えたい一面があることが理解されにくいのですが、楽しい語らいのある愛情いっぱいの家族を本当は求めています。
究極のエニアグラム P233
要するに、我が強く家長的な役割を果たす人が多いわけですね。
ちなみに性格のタイプでは「恐れと傷つきやすさを抑え込んで、しなければならない挑戦はどんなものにでも応じられるように、強くあろうとするようになる」とあります。
それぞれの書籍にある共通点と相違点をまとめてみましょう。
共通点
果敢に挑戦する家長タイプ。我が強く自分で決めるタチ。
相違点
挑戦が「自主的にするもの」なのか、それとも「せざるをえなかったもの」なのか。
大体こんな感じでしょうか。
おおよそ自主的にせよ強制的にせよ、困難や窮地においては果敢に挑むことができる強烈さがあるという点において共通点があります。
また、我の強さもどちらも持ち合わせていますね。要は自分のことは自分で決めて、自分の力で道を切り開いていく性格という感じです。
リーダーになりたい子供なのか
「タイプ8はリーダーになりたい」という感じの風潮があります。これはほぼ正解といったところですが、これは子供にも当てはまるのかというと、答えは「YES」です。
必ずしもリーダーになりたい子供ばかりかというとそうでもありませんが、大抵は影響力を持って場を支配したい子供ばかり。だってそれが本人たちにとって一番安全ですから。
当然、自分の意見を強く反映させようとしてきますね。そのために手段を厭わない子も中にはいるでしょう。
全員がそうではありませんが、やはり影響力を発揮するため、ひいては自分の身を守る強さを手に入れるためには、リーダーとして周囲を想うままに操ることが一番楽なのです。
自分の身を守りたい
究極、大抵の行動は根源的欲求にかかってきます。
タイプ8がリーダーになりたいのも力を求めるのも、大体は自分の身を守りたいから、そして自分の影響下にある人や家長として守るべき人を守りたいからに他なりません。
当然、その気持ちは子供時代から育まれているわけです。
タイプ8の子供は独立心が強く、非常に頑固なところがあります。これはタイプ8のほぼ全ての子供に共通する特徴でしょう。
その独立心も頑固なところも、結局は自分以外に信用できるものがないという気持ちの現れです。
究極、親すらどこか疑っている。信用していない。これが、タイプ8の子供の実態なのかもしれません。
たまにいる例外的なタイプ8
タイプ8の家庭環境は大半が機能不全だったり、そうでなくても波乱が多いのはちょっと否めません。実際、いくつかの書籍でも明言こそされていませんが、それっぽい記述が記されています。
というわけで、相当に荒んだ環境で生きてきたタイプ8もそれなりにいるわけですね。
子供ながらに家長の代わりとしていろんなことを取り決めたり決断したりしていくことが多い、あるいは虐待やネグレクトから我が身を守ろうとすることも多々あるタイプ8の子供たちですが、当然子供の身では限界というものがあります。
そういう時にどうなるのかというと、退行です。
タイプ8の中には、恐ろしく大人しく、そして自分の身を守るのに手一杯で、非常にビクビクした子供、あるいは周囲のなすがままになっている子供も存在します。
こういう子供たちの中にも当然自我ややりたいことはあるのですが、多くは学習性無気力に陥っている状態。本当は自我が強いのにそれを表に出せず、非常に鬱憤やイライラを溜め込みやすい状態に陥っている場合も少なくないと私は思います。
こういうタイプ8の子供は皮肉屋な一匹狼としてクラスの問題児になったり弱いものいじめに走ったり、あるいは発散できずに常にストレスを抱え続けることにもなるかもしれません。
それとも、すべてを諦めて手放したような子供もいるかもしれませんね。こういう子供はタイプ8かどうかによらず、達観してすべてを悟ったような性格に収まることが多々あります。
タイプ8だと見分ける方法
で、こういう達観して諦めきった子供、ビクビクして何もできなくなった子供をタイプ8だと見分ける方法ですが……(かなり難しいですが)1つ心当たりがあります。
それが、「勝ち負けやできるかどうかをかなり気にする」というものです。
例えば「どうせ負ける」「どうせできない」というのが口癖になっていたり、「無理」と言いつつ一応やろうとはしたり等……。言葉の端々に「勝ちたい」「やり遂げたい」という気持ちが見え隠れする子供は、もしかしたらタイプ8かもしれません。

「できない」「無理」と言いつつ結局行動しようとする子供は、結構タイプ8要素が強い可能性がありますね。
だって無理だと思ったら普通はやらないじゃないですか?どうしてやろうと思ったんだよと。
あとあれだ。ひねくれた子が多い
いろんなタイプ8がいる
タイプ8に限らず、どのタイプも色々ですね。結局人間を9つのタイプに無理やり分類しているわけですから、当然テンプレタイプからかけ離れた子供も出てくるわけです。
とはいえ、見分けが完全につかないわけではありません。
特に勝ち負けやできるかどうかを幼少期にやたら口にしていた場合、一度タイプ8の要素を疑ってみてもいいかもしれません。
お子さんの場合も同様ですね。やりたいことをお子さんが示した場合は、一度やりたいようにやらせて様子を見るのも一興……かも?
といったところで、今回はここまで。
普通のタイプ8解説もやってますので、よろしければそちらもご覧くださいませ。
筆者:春眠ねむむ
X :@nemukedesiniso
threads:@shunmin.nemui
参考書籍
エニアグラム解説
タイプ一覧
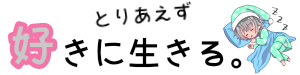






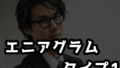

コメント