今回はちょっとした考察回ですね。タイプ5が何をストレスとしているのか、そしてその心の繊細さについてちょっと考えていこうと思います。
実際、繊細さんは結構多いと思います。だからこそ引きこもるし、場合によっては他人を攻撃するわけです。
ともあれ、前書きでいろいろ語っても仕方ありません。早速考えていきましょう。
タイプ5のストレス源
このタイプはとにかく自分の時間がないとイライラしやすく、しかもそんなイライラした自分に対してさらにイライラとループを引き起こすことも少なくないタイプです。
というのも、結構強い感情とか濃密な関わりとか苦手なタイプ。
本能がセクシャル優位でもない限り、自分の感情が他人に向くことはほとんどないと見てもいいでしょう。
とりあえずストレス源になりそうなものを私なりにまとめると、こんな感じ。
・1人の時間が取れない
・あまりに濃密すぎる人との関わり
・激情や強すぎる刺激
・自分の無能・無力を思い知ったとき
・何かに没頭できる時間がない
・自分の好きにできる時間を確保できない
おおよそ、1人で好きに研究したり探求する時間が好きな人たち。だからその時間がないとまずメンタルが死にます。
そして当然強すぎる刺激や感情を向けられるのもNG。このタイプにとって、それらはこのタイプが麻痺させた自分の感情を想起させます。
つまり、無理やり叩き起こされたようなものですね。基本的に自分には現実に立ち向かう力がないと思っているタイプなので、そうやって無理やり外界と濃密に触れさせる行いは危険と言えます。
ある意味、趣味に没頭したり1人の時間をとにかく欲しがるのも、現実に立ち向かう力をつけるための行いだったりします。
また、そんな感じで自分の無力を噛み締めているタイプなので、無能や無力を外界の出来事から感じてしまうことにも非常に弱いです。

優しい人もいる反面妙に攻撃的な人もいるタイプですが、攻撃的な理由はそれだけ外界を恐れているともとれるわけですね
ストレスを感じるとどうなるのか
では続けて、タイプ5がストレスを感じるとどうなるのかを見ていきましょう。
ぶっちゃけてしまえば、退行(分裂)ですね。タイプ7が不健全になったかのような振る舞いをします。
例えば普段は行かないような刺激の強い場所(ギャンブルやナイトクラブなど)に立ち入ってどハマりしたり、あるいは酒やタバコにどっぷり浸かってしまったり、宗教に救いを求めたり……。
これらの行動は、自分の苦しみから目を逸らすための一時的な措置に過ぎませんし、根本解決にはつながりません。
ですがどうしようもなくなったタイプ5は、藁をもつかむ思いで何かに救いを求めるわけです。
タイプ5の繊細さについて
さて、ストレス源と退行の原理についてお話ししたところで、いよいよ繊細さについて色々と考えていきましょう。
と言っても、難しいことではありません。このタイプの肝は、自分には世界で戦っていく力がない・自分は無能だという考えが心のどこかにあって、それがいろいろなものに蓋をする要因になっている点です。
蓋をするものは例えば自分の欲求であったり、感情であったり、本当の気持ちであったり……。
タイプ5には、自分のニーズを必要最小限に止めることで世間との関わりをほとんどなくすという、ある種の癖があります。
つまり、「あれも欲しい」「これも欲しい」とはならないわけですね。
部屋も食事も粗末なものでいい。ただ自分だけの空間と、趣味や探求に没頭できる時間があれば、それだけで構わない。
世間との関わりを絶つことで閉鎖された空間を作り出し、その閉鎖空間で自分の力を磨き、世に出る準備をする。
究極、タイプ5がやりたいのはこれです。
現実を想起させるものは嫌い
となれば、です。おそらくですが、タイプ5が嫌いなものは現実を想起させうるものと言っても決しておかしくはないのではないでしょうか?
例えるなら、準備不足で無理やり戦いの場に引き摺り出されるとか、素手で猛獣と格闘させられるとか。
タイプ5にとって、現実を想起させられるというのはそういう意味を持つのかなと思われます。
「自分はとてもではないが現実世界で生きていけない。だから少しでも準備をさせてくれ」と。
おおよそ、タイプ5の本音はそう言った感じなのかもしれませんね。
現実を直視するということは、すなわち準備不足のまま戦いの場に赴くこと。
あるいは自分の無能と失態を晒すのと同義。
そう考えると、なんとなくタイプ5の輪郭が見えてくる気がします。
感情を隠す
また、タイプ5には「自分の感情を自分自身が感じないようにする」というちょっと変わった性質があります。
例えば怒りを覚えてもそれを感じないようにしたり、本当は楽しいのに表層意識では楽しいかどうかわからなかったり……。
この感情を隠す(というか麻痺させる)行為も、言ってしまえば自己防衛の結果ということなのでしょう。
生の感情を自分が感じてしまえば、それすなわち現実に生きていると同義。
タイプ5は、準備が整うまでは現実に生きたくないわけです。
だから生の感情を出すのも嫌だし、本音や欲求を自覚するのも嫌。全ては自分がそれらを出すにふさわしい時が来るまでとっておく。
同時に、「生の感情に振り回されては自分のやりたいことに没頭できない」と感じているところもあるでしょう。表層意識では、むしろこっちが強いかもしれませんね。
結局のところ、自分が生きていくには一芸を極めるしかない。自覚があるにせよないにせよ、そう感じているタイプ5は多いはずです。
となれば、自分のやりたいことを妨げる要素は全て邪魔。感情も邪魔なものの一つ。
そういうわけで、感情を封印してもおかしくはないと私は思います。
強い感情には圧倒される
強い感情には圧倒され、言葉を失うような気持ちを覚える。これもタイプ5の口から出た言葉の一つです。
もともとタイプ5は、そこまで感情を自覚できる人たちではありません。なぜなら、その感情が自分の準備を妨げるから。邪魔だから。
しかし、もう一つ理由があります。
それが、生の感情が怖いから。これは自分のものも他人のものも、両方が含まれます。
結局、タイプ5にとって生の感情とはどこまで行っても現実のそれであり、生きている実感なのでしょう。
だからこそ、怖い。だからこそ避けたい。なぜなら、それは自分が強くなるまで避けていたいものだから。
そう考えると、なんとなくタイプ5が感情を捨てる意味も見えてきます。
感情を「自覚する」ことならある
例えば感動とか、畏敬とか、あるいは共感とか……そういう感情を自覚することならば、(苦手ながら)タイプ5にもあります。
ですが、やはりどこか他人事なんですよね。自分が主体になることがない。
ある意味ではここがタイプ4との違いになるのでしょうか。
自分の感情を自覚し、「ああ、こういうことか」と理解し、どんなものなのかを分析する。それで終わりです。
下手をすると、その感情を自覚するのが数日後とか、かなり遅れてくることもあります。要するに、自分の中で発覚するまでは正体不明の何かです。
このように、自分の感情を味わうとかしっかりと受け止めるという点においては、タイプ5は非常に疎いです。下手をすると、それらを不要なものとすら思っているかもしれません。

感情は感じるのではなく分析するもの!
……こういうこと言ってるからダメなんだろうなぁ……
繊細さゆえに自分の感情を捨てる
タイプ5は思ったよりも繊細で深みのある人たちです。
ですが、その感情を表に出すこと、ひいては自覚することを非常に嫌う人たちでもあります。
なぜなら、自分がその感情に圧倒されるから。
そしてその感情は自分を殺しかねないものだから。
タイプ5は、しばしば冷たいとか感情がないみたいに言われることがあります。しかし、それは間違いと言っても良いでしょう。
なぜなら、そこにあるのは感情への恐怖と忌避感。感情がないのではなく、避けたいという気持ちがあるだけです。
実際のタイプ5は、多感で繊細な人たちです。
繊細さゆえに感情に振り回されないよう自分の気持ちを麻痺させ、感情に向き合わないようにしている。おそらくはこれが正解でしょう。
結局人間である以上、感情のないロボットみたいな存在はほぼゼロに等しいです。
タイプ5も感情を味わうことができないだけで、しっかりとどう感じたかは存在しているのです。
筆者:春眠ねむむ
X :@nemukedesiniso
threads:@shunmin.nemui
参考書籍
エニアグラム解説
タイプ一覧
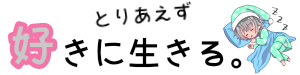







コメント