エニアグラムは、何かと3、3、3とタイプを3つのグループに区分けする方法が多いです。
有名どころだと、そのうちのひとつがセンター、ひとつがホーナイの分類。そしてもうひとつが、今回のハーモニクスですね。
楽観的グループ、合理的グループ、反応的グループの3グループに分類されるハーモニクスですが、今回はそんなハーモニクスとは何なのかを見ていきましょう。
ハーモニクス=問題解決の方向性
人間、生きていれば何かしら問題や壁にぶち当たります。
で、その問題や壁が何なのかとか、あるいは壁にぶつかった時にどうするのかは人にそれぞれですね。
例えば「人から嫌われたくない」とか、「自力解決できない袋小路は嫌じゃ!」とか、どうしても避けたい問題は人によって異なります。
反応にしても、考えるより先に逃げたり、立ち向かったり、あるいは責任逃れと自己防衛に徹したり……
今回見ていくハーモニクスの概要を簡単に言うと、「各タイプが重大な問題や困難にぶつかった時にどう反応するのかを三分類にしてみました」と言った感じになります。
ハーモニクスは、そのタイプがおもなニーズを果たせなかったとき、どのような態度を取るか、教えてくれます。
つまりハーモニクスは、私たちが葛藤や困難にどう対処するかを示してくれているのです。
エニアグラム【実践編】 P39より引用

これもホーナイの分類同様、人間関係で出やすい特徴のようですね。
人と対立するとか親しい人と喧嘩するとか、あるいは誰かに不満を持った時に出やすいです
困難の多くは、根源的恐れ、あるいは囚われに大きく関係します。やはりどちらも見たくないものや感じたくないもの、そしてそれから逃げるための行動の詰め合わせですからね。
自分が不安に感じることやよくやる行動の癖を知っておくと、それだけ自分自身の問題や課題が見えてきます。
ハーモニクス、3つのグループ
さて、概要を話し終えたところで、ここからはハーモニクスによる3つのグループを見ていきましょう。
ハーモニクスの区分けは、以下の通り。

楽観的グループ:タイプ2、タイプ7、タイプ9
合理的グループ:タイプ1、タイプ3、タイプ5
反応的グループ:タイプ4、タイプ6、タイプ8
自分や他人の求めるものや悲観的な部分から目を逸らす楽観的グループ。
社会やシステムとの関わり方がネックの頭で考える合理的グループ。
そして感情的な反応多めで人間関係に何かしら問題を感じやすい反応的グループ。
簡単な区分けは、こんな感じですね。
楽観的グループ
楽観的グループ:タイプ2、タイプ7、タイプ9
これらのタイプは、基本的に楽観姿勢が強い人たちですね。
何かしら大きな挫折を味わっても、まず感じることは「まあ何とかなるか」。心がタフですね。
自分が基本的にいい気分でいたいため、周りが暗くてどんよりしているのが何より嫌い。明るく振る舞い、周囲の気持ちを高めてくれるムードメーカーです。
ですが反面、自分の暗黒面と向き合うのが苦手で、心の闇を完全にスルーしがちな共通点があります。
自他のニーズのバランス取りが鬼門になりやすく、気持ちや感情がぶつかる様を見たり感じるのは大の苦手です。
意図的に暗い話題を変えたり深刻な話を避ける傾向があり、特に痛みや苦しみが伴うような問題を基本的にノーサンキュー。
「問題解決とかどうでもいいから仲良くやろうよ」とか考えちゃうタイプですね。
そのため、決定的な亀裂や状況を軽視してしまうことも少なくありません。
| タイプ | 重点を置くこと | 見たくないもの | 自他のニーズへの対処 |
|---|---|---|---|
| 2 | 思いやりと深い愛情を持つ善人であるという自己像。 自分の善意や優しさばかりに注目する事もある。 | 自分の悪感情、暗黒面。 特に怒りや失望、欲求。 | 自分の問題やニーズを無視して人に尽くす。 自分のニーズを完全無視。 「私いい人でしょ?」 |
| 7 | いろんな楽しいことを満喫しまくる愉快な日々。 エキサイティングな出来事。 | 自分の心の苦しみ、悲しみ、葛藤。 そんな苦しみを自分が生み出しているという結論。 | 自分の楽しみやニーズばかりに集中する。 人のニーズを重荷に感じて苦々しいものとして扱う。 最悪自分の楽しみだけを見ればオールオーケー。 |
| 9 | 自分やみんなにとってのいいこと。物事のポジティブな側面。 自分の脳内の理想の世界。 | 気に入った人たちや自分の問題や葛藤。 自分や周囲が成長しないという事実。 | どっちつかず。 自分も他人もハッピーになろうとどちらのニーズにも全力を尽くすが、中途半端に終わってしまう。 |
合理的グループ
合理的グループ:タイプ1、タイプ3、タイプ5
個人的な感情を脇に置いて、頭で問題の合理的解決を図ろうとするタイプ。能力志向になりがちで、よくも悪くも「有能で優れている」という自己イメージに固執しやすい傾向にあります。
客観的で論理的な視点を持って問題解決を図ろうとするタイプで、主観的なニーズや個人の感想、情緒よりも、「こうしたらいいじゃん」という考えを優先しがちです。
自他共に「こうすべき」「こうする方がいい」を優先するのが一番いいとどこかで信じてすらいます。
このグループに共通するのは、社会的なルールやシステムをどこまで意識するのかという点です。
世間の常識やルールという縛りの中で問題解決を目指すのか、それともルールを一旦無視して解決法を探すのか。ここに大きな違いが出ています。
| タイプ | 重点を置くこと | 気持ちへの対応 | システムへの態度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正しく分別があり、万事きっちりしていること。 ルールや基準志向。 | 抑圧的。自分の気持ちを押さえ込み、完璧な行動や仕事ぶりに昇華させる。 問題解決への逃避。 | 恭順的。システムにとって「いい子」でいたい。 ルールや常識を絶対視しがちで、守らない奴は見ててムカつく。 |
| 3 | 有能で周囲から称賛されるべき人であること。 目標や効率重視。 | 目標達成に邪魔なので無視。目標の達成感や自己顕示によって埋め合わせようとする。 「どう思った方がいいのか」を探り、演じようとする。 | 中立中庸。ルールや常識に従うことでメリットを享受したいが、そのために縛られるのも嫌。 あくまで効率とメリット重視なので、場合によってはルールの意味を意図的にねじ曲げたり曲解する。 |
| 5 | 専門的で何かを知り尽くしていること。 客観視や論理性を重視。 | 切り離す。物事を概念や事実として見ることで他人事のように感じる。 思考や思索への逃避。 | アンチシステム派。そんなもの制約でしかない。 そんなことより一人でやっていきたい思いが強く、縛られるほど抜け道や逃げる方法を大真面目に考える。 |
反応的グループ
反応的グループ:タイプ4、タイプ6、タイプ8
感情の起伏が比較的大きく、問題があるとまず感情的に反応します。
人間関係においてはまず感情的にアプローチすることで自分の要求を通したり、相手と繋がり合おうとします。
例えば怒ったり泣いたりして相手を動揺させたり、感情的な反応を引き出して相手を理解しようとしたりなど……何かと感情に重点を置きやすいグループです。
人とのつながりや信頼関係についてネックになりやすく、ついつい相手の反応を見て「信頼できるかどうか」を見ようとする人たちですね。
何かしら問題点や不安点があれば、人に言わずにはいられません。「相手に自分を知ってほしい」という気持ちが強いので、ついつい相手に「どう思う?」と反応や共感を求めてしまうのです。
まずは、問題解決よりも感情の対処が優先的。感情さえ落ち着けばすぐに問題は自己解決していきますが、もし気持ちが収まらなかったときは大暴走してしまうこともあるでしょう。
| タイプ | 人に求めること | 恐れていること | 人への反応 |
|---|---|---|---|
| 4 | 親役。自分を救ってくれる救世主の存在。 私の夢を一緒に叶えて。 私を見つけて。 | 誰からも気にかけられず、見捨てられること。 誰も自分のことを見てくれず、支えてくれる人がいないこと。 | ツンデレ大作戦。気の無いフリやデレデレの姿を使い分けることで、周囲の関心を引こうとする。 |
| 6 | 親役も子役も両方。自立したいが人にも頼りたい。 自分が頼ることができる人が欲しいが、最悪自分自身が強くなる。 | 見捨てられること。 自分の心の支えになるものがひとつもないこと。 でも警戒心が強いので、依存して自立を失うのも怖い。 | 頼れる存在になることで、一定の自立を果たそうとする。 でもやっぱり誰かいて欲しい時もある。 自己防衛的でたまに刺々しい時も……。 |
| 8 | 自我を保つため独立独歩。強いて言えば子役が欲しい。 できれば人に頼りたくないが、信頼できる数名にベッタリになる事もある。時には支えが欲しいのだ。 | 誰かから支配されたりコントロール下に置かれる事。にんげんこわい。 誰かを信頼しすぎて自分が弱くなってしまう事。 | 隙を見せずドッシリ構える。 自分の心の傷や苦しみは見たくない。だって弱くなるもの。 タフネスあるのみ。 |
まとめ
結論を言うと、以下のとおりですね。
楽観的グループ:問題をガン無視して気楽に構える
合理的グループ:問題解決にしか目がいっていない(他の要素を顧みない)
反応的グループ:人の反応や感情を何かと見たがる
三者三様、致命的な問題への対処は良い面も悪い面もあります。どの方法が優れているとか劣っているとかはありません。

字面だけだと、合理的解決が一歩先を行ってる気もしなくもない。
でもどれだけ解決法を提示しても誰も受け入れてくれないばかりか、みんなから敵視されることが多いんですよね……なぜじゃ
ともあれ、事の本質は優劣ではありません。あくまで本題は、「それぞれのタイプにこういう傾向の癖がある」というのを知ることです。
ハーモニクスで同類に分類されてるタイプは、非常に誤認が多い組み合わせでもあります。
例えばタイプ7の人が自分をタイプ2やタイプ9と思ったり、タイプ6っぽい人にはタイプ4やタイプ8を自認する人が多かったり……逆も然りです。
当然最終的には「その癖から自分の欠点や心の傷を理解すること」が目標になってきますが……一旦は「こういう分類の仕方もあるのか」と知っておくくらいでも全然使える知識です。
よろしければ、ここで「しっくりくる」と思ったタイプを一度検討されてみてはどうでしょうか?仮に的が外れても、状況はマイナスには転ばないはずです。
筆者:春眠ねむむ
X :@nemukedesiniso
threads:@shunmin.nemui
参考書籍
エニアグラム解説
タイプ一覧
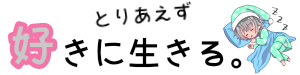






コメント